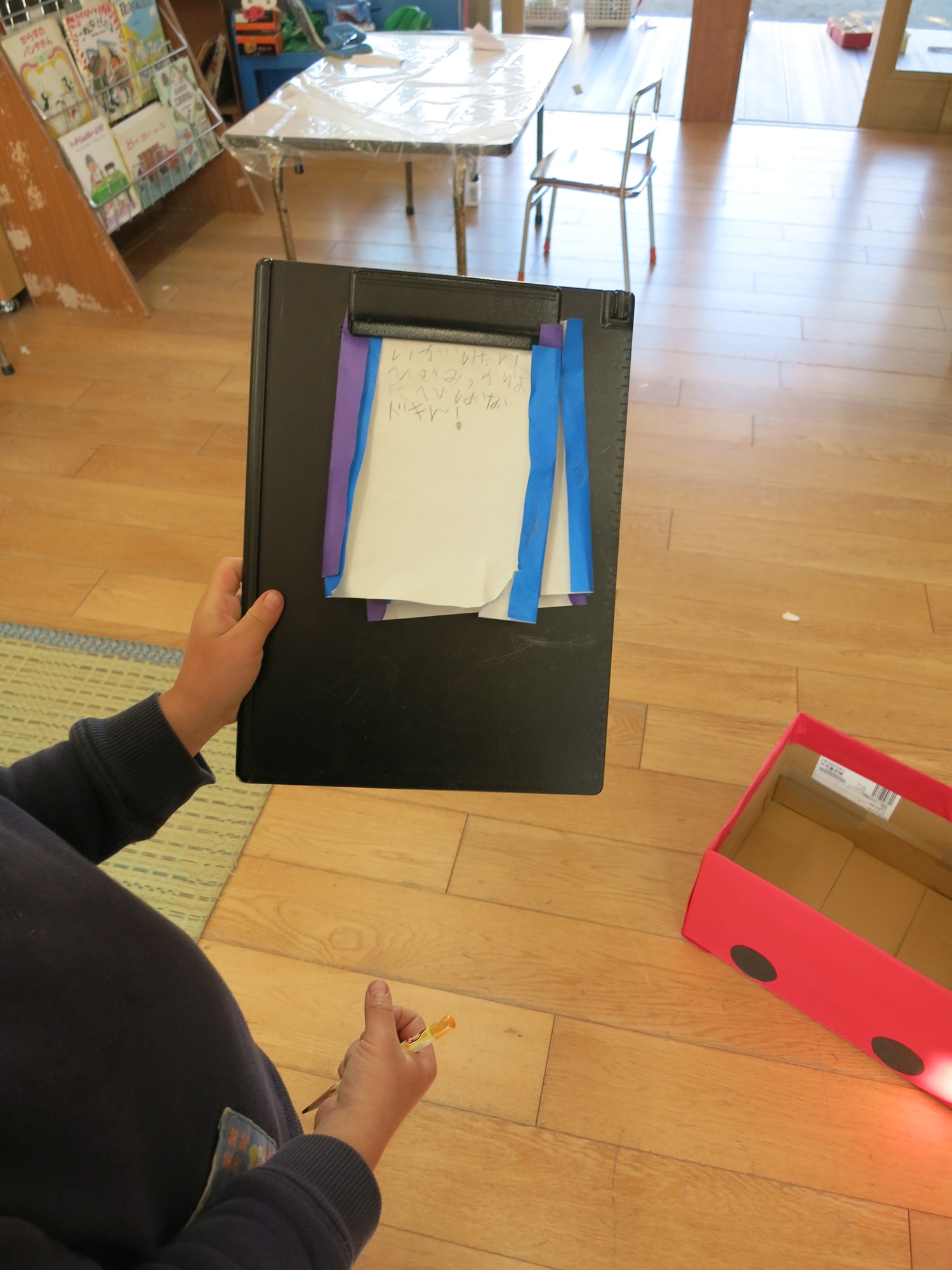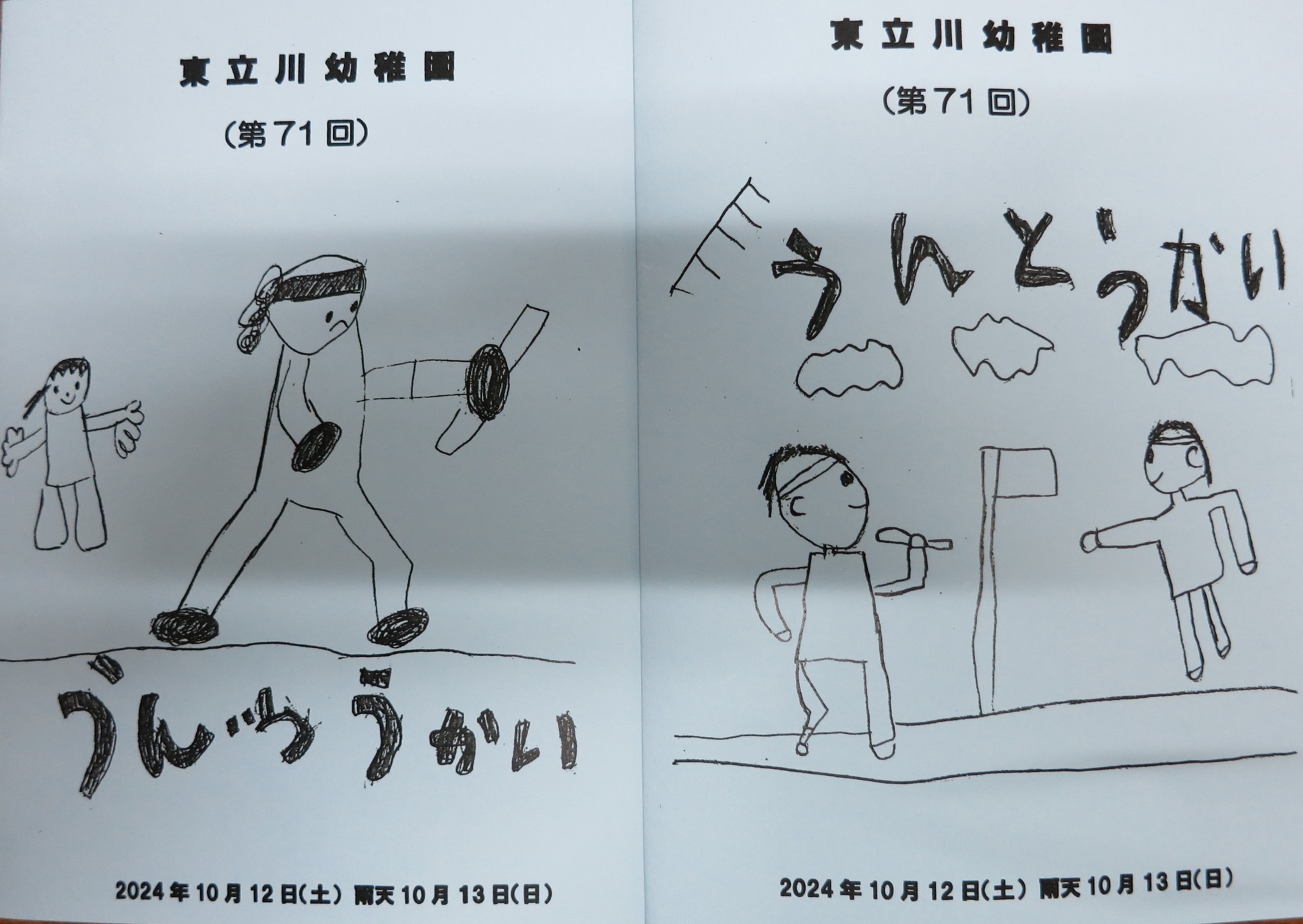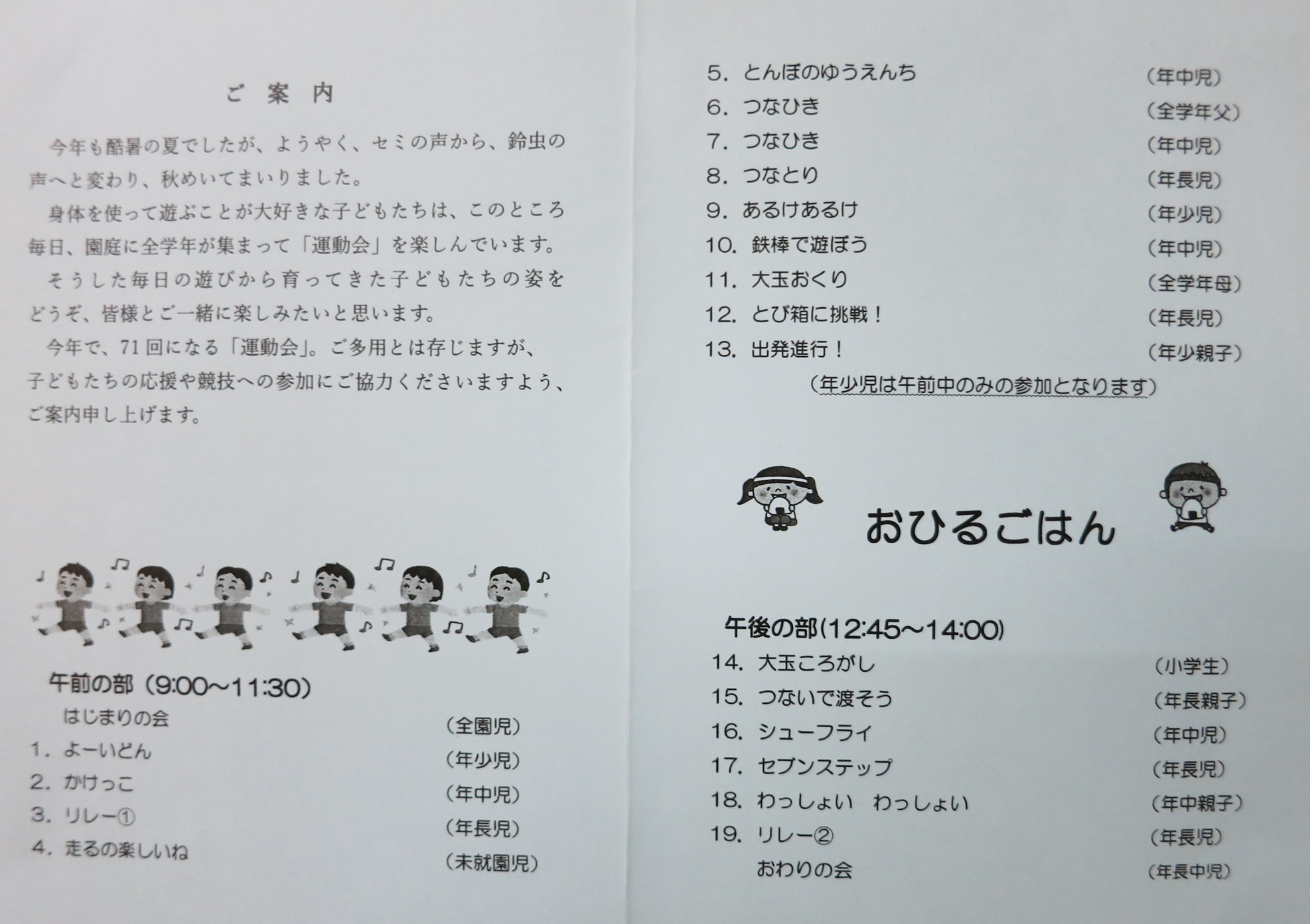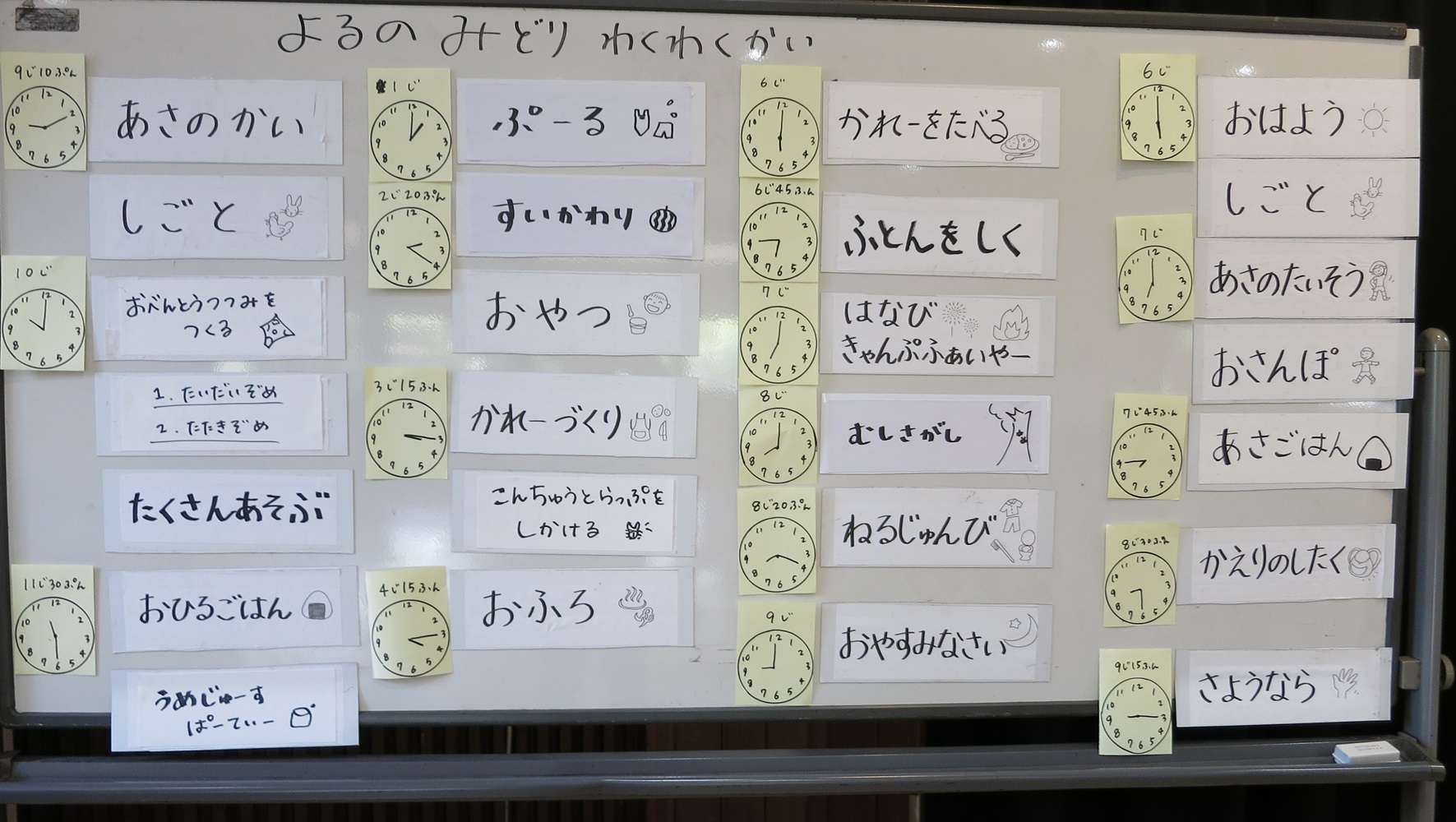11月頃に一度、収穫しましたが、その味が忘れられない子どもたちから「また、とって!」のリクエストがあり、2月末に高ばさみが届く範囲の夏ミカンを収穫しました。その数、ざっと300個。本当にお店ができるほどでした。
エッ?“いい年をして、一人で高いところに登り、危なくない?大丈夫だった?”ですって・・・。
ご心配なく。ちゃんと、子どもたちが手伝ってくれましたよ。夏ミカンを拾い集め、籠に入れることから、籠の運搬、机の上への展示などなど・・・。5歳児を中心に「次は何やればいい?」と、本当に積極的に手伝ってくれました。大人から仕事を頼まれ、その手伝いをすることも意外に楽しいようです。
「ありがとう。本当に助かるよ!」そんな私の声かけも励みになったようです。
そう言えば、幼児教育では遊びだけでなく、他者と生活する中で、役に立つ喜びを感じる姿を「有用感を味わう」と捉え、とても大切にしています。進んでお手伝いをしてくれた子どもたちは、そんな実感を持ってくれたのかもしれません。
そんなお手伝いの中で、とても印象的だったのが5歳児のAちゃんの姿でした。
夏ミカン並べに夢中になっているクラスメートの姿をよそに、カットした夏ミカンの茎や葉を私が掃除していると、もくもくと拾い集め、ゴミ袋に入れてくれました。幼児にとっては気づきにくい作業だと思いますが、Aちゃんはそれが必要だと考え、一生懸命、取り組んでくれました。しかも、その頑張りを誇ることもなく、本当に最後までキレイに片付けてくれました。
教師はとかく、こちらが期待する姿を示す子、あるいは、リアクションの良い子に注目しがちです。まぁ、自分が思う通りに教育実践を進めるためには、その方が都合がよいですからね・・・
でも、その姿勢は子ども一人ひとりの気づきやこだわりを見落とすことになります。目立ちにくい姿に気づかず、その子なりの努力や工夫を認めることもできません。「ど真ん中」と見えがちなルートを堂々と歩む姿だけでなく、目立ちにくい歩みを進める子どもにも目を向けていかねばなりませんね。
Aちゃんが黙々と片付けに取り組む姿から、そんなことを気づかされました。本当にAちゃん、ありがとう。ステキでしたよ!